持久力とスタミナ・鉄分の関連性、夏バテに負けない食事の特徴・ヘモグロビンの働きのまとめ。
◆持久力をつける食事・スタミナと鉄分の関連性(もくじ)
- ⇒持久力をつける食事・栄養素とは?
- ⇒誰もが知っているはずの鉄分の秘密
- ⇒あの選手のスタミナは桁違いだよ!
- ⇒持久力とは?
- ⇒スポーツ選手はスタミナが重要な指標のひとつ
- ⇒夏のスタミナ料理の定番「レバニラ炒め」や「スタミナ丼」などのメニューのポイント
- ⇒鉄分を豊富に含む食品を摂取していれば夏ばて予防になる
- ⇒女性は「めまい」や「易疲労感」「動悸」といった貧血の症状を発症しやすい
- ⇒女性は鉄欠乏性貧血になりやすい
- ⇒なぜ鉄分が不足すると貧血を発症するのか?
- ⇒ヘモグロビンの材料である鉄分が不足するとヘモグロビン濃度が低下する
- ⇒鉄分を失うとヘモグロビン濃度が低下する
- ⇒スポーツジムではトレッドミルやエアロバイクといった有酸素運動マシンが人気が高い
- ⇒有酸素運動マシンは持久力を高める
- ⇒酸素がポイント?
- ⇒汗と一緒に鉄分やナトリウムなどのミネラル成分も体外へ
- ⇒運動性貧血とは?
- ⇒酸素供給量が低下すると心肺機能・持久力・体力も低下を招く
- ⇒改めて鉄分と持久力の関連性を問う
- ⇒鉄分摂取のポイント!ビタミンCを同時に摂取すると体内への吸収率が高まる
- ⇒サプリメントから摂取するポイント
- ⇒鉄分の吸収を高めるビタミンC
◆持久力をつける食事・栄養素とは?
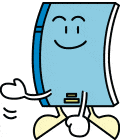
食事をするだけでスタミナや持久力が大きくアップする!!
もし、本当に効果的に持久力をアップできるサプリメントや食材があるのであれば誰もがぜひ取り入れていきたいと思う事だろう。
ただ食事やサプリを摂取するだけで持久力がアップする。
そんな夢のようなサプリメントが実在するのだろうか?
いきなり結論となるが、摂取するだけで持久力と呼ぶ能力を高める魔法のようなサプリメントは存在しない。
当り前である。
しかし、「自分に既に備わっているレベルの持久力」を最大限に引き出し発揮させる可能性を高めるサプリメントや栄養素は存在する。
この答えが誰もが知っているがそこまで意識付けされる事のない「鉄分」である。
◆誰もが知っているはずの鉄分の秘密
まず一度わかりやすく数値で例えてみよう。
自分に既に備わっている「持久力という能力」があったとする。
持久力と呼ばれる能力は様々な要因が関与して構成される為、一概に数値化できるものではないが、ここでは理解しやすいように数値で見ていく。
※あなたの持久力最大値が仮に100の場合
試合時間の経過と共に疲労が蓄積し、どんなに頑張ったとしても全力の60%程度しか能力を発揮できない状態である場合。
その時点でのあなたのMAXの持久力は60となる。
これはわかるだろう。
しかし、試合時間が経過しても、体中の隅々まで能力を発揮できるような状態が継続的に整っており90%程度まで能力を発揮できる状態を維持する事が可能な状態であったならばあなたのMAXの持久力は90となる。
これはシンプルに大きな差だ。
まぁ、「そんなのは理屈で実際にそんな場面はないでしょ?」
そう思われる方も多いかもしれない。
確かに90%と言えばかなりハードなレベルのライン、実際に常に100%に近い能力を何時間も発揮することは不可能である。
これはそもそも人間の体の仕組みがそうなっているからだ。
しかし、この持久力という能力に大きく関与する成分があり、その成分の状況によっては発揮できる能力値を高めることができるのも事実である。
その成分こそが、誰もが知っている「鉄分」と呼ばれるミネラル成分である。
◆あの選手のスタミナは桁違いだよ!
「いや~あいつはバテないなぁ・・・・」
「試合の後半なのにあのチームはスピードが落ちないね。」
「あの選手のスタミナは桁違いだよ。」
こんな会話が日常生活の中にあるかどうかは微妙かもしれないが、言葉が違えどこのようなニュアンスの会話をあなたも耳にした事、もしくは口にした事があるのではないだろうか?
これらの言葉に共通する概念のひとつに「持久力」というものがある。
◆持久力とは?

持久力とは、いわゆるスタミナのこと。具体的には「長時間運動を継続する能力」、もしくは「長時間に渡って一定の運動レベルを保持する能力」が持久力である。
試合の後半ラスト間際の場面。
通常、試合時間の経過と共に筋肉の内部には疲労物質が蓄積する。
この疲労物質の代表が「乳酸」と呼ばれる代謝産物。
この乳酸は悪者に見られがちであるが、エネルギー代謝の産物でありこの乳酸は新たなエネルギー源として活躍するスポーツアスリートにとっては非常に重要な物質でもある。
また乳酸の他にもATP系の分解によって代謝された代謝物やアデノシンもこの筋肉に蓄積していく。
このような状況下においても試合開始とさほど変わらないようなパフォーマンスを見せるアスリートがもしいたならば、その選手は持久力がある選手。
「すごいスタミナだ~!」と思わせる選手であることは間違いないだろう。
仮に周りの選手の能力が極端に落ちた状態で、その選手のパフォーマンス低下率が低かった為にそのように見えたとしても同じこと。
周りの選手よりもバテにくい体。
バテにくい何かしらの原因があると言える。
◆スポーツ選手はスタミナが重要な指標のひとつ
スポーツアスリートは実践している競技種目にもよるが持久力が上昇するだけで有利になる種目も多い。
その筆頭は陸上の長距離選手、マラソンランナーであろう。
実際、42.195キロもの距離を100メートル平均にして15秒~17秒台というスピードで走り続けるフルマラソンに至っては持久力がないアスリートの場合完走も難しい。
この他にも持久力が不可欠と言えるスポーツは幾つもある。
★バスケットボール
★バレーボール
★サッカー
★水泳
★駅伝
★ラグビー
★テニス
★スキー
★クロスカントリー
★フットサル
あげれば切がない話になるが、様々なスポーツ種目においてスタミナが重要な要素のひとつであることは間違いないだろう。
◆夏のスタミナ料理の定番「レバニラ炒め」や「スタミナ丼」などのメニューのポイント
夏場になればよくお目にかかる「スタミナ弁当」や「スタミナ丼」などのメニュー。
これらの弁当に入っている食品を見ると焼肉などの肉系の食材が多い。
夏のスタミナ料理の定番であるレバニラ炒めなどもそう。
これらの食材、食品に共通する点のひとつに鉄分やグルタミンが豊富であるという共通点がある。
ここまで見ていくと、何となく「夏ばてには鉄分を採ればいい」というイメージが沸いてきたと思う。
◆鉄分を豊富に含む食品を摂取していれば夏ばて予防になる
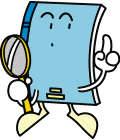
鉄分が豊富な食品と言えば、ポパイで有名な「ほうれん草」や「小松菜」、そして「モロヘイヤ」や「にら」などの野菜類。
そして「豚レバー」「鶏レバー」「はつ」などの内臓系の肉類。
「ひじき」や「のり」「わかめ」などの海藻類のレシピが定番である。
鉄分を豊富に含む食品を摂取していれば、夏ばて予防になる。
そう思って鉄分を一生懸命摂取することは間違いではない。
しかし、スポーツアスリートとしては、この鉄分がどのように働き、どのように持久力、スタミナに関与していくのかを把握しておくことのほうが重要である。
なぜなら、鉄分そのものがパフォーマンスに影響を与えている訳ではない為である。
◆女性は「めまい」や「易疲労感」「動悸」といった貧血の症状を発症しやすい
鉄分が不足すると貧血になる。
これは聞いたことがあるだろう。
このように体内の血液中に含まれている鉄分が不足し、ある一定ライン以上の鉄分を失うと人は貧血症状を発症する。
鉄分が不足することによって発症する貧血は鉄欠乏性貧血と呼ばれる。
我々が発症る可能性が最も高い貧血症状も、この鉄欠乏性貧血である。
※鉄分の不足によって発症する貧血=鉄欠乏性貧血
◆女性は鉄欠乏性貧血になりやすい
統計では鉄欠乏性貧血の貧血症状を発症する男女性別の割合は70%以上が女性に発症する傾向にあるとされている。
年代によっても異なるが、それでも男性にも意外と多く発症する可能性があることに驚いた。
女性が圧倒的に貧血を発症する可能性が高いのは、月経の影響が大きい。
月経では血液の出血に伴い、血液中に含まれている鉄分も同時に失うことになる。
その為、女性は「めまい」や「易疲労感」、「動悸」といった貧血の症状を発症しやすい。
◆なぜ鉄分が不足すると貧血を発症するのか?
鉄分が不足すると貧血になり、鉄分の不足によって発症した貧血は鉄欠乏性貧血と呼ぶんだな。
よし理解したぞ!でも待てよ・・・・
そう、ここでひとつ疑問が沸く方もいるだろう。
「そもそも何で鉄分が不足すると貧血になるの?」
そう貧血に至るまでの経緯の問題である。
さあここから当サイトの本題への突入である。
◆ヘモグロビンの材料である鉄分が不足するとヘモグロビン濃度が低下する
鉄分が不足すると貧血症状になりやすい。
「では、なぜ鉄分を失うと貧血症状に陥りやすいのか?」
貧血症状をもたらす要因に大きく関与する血液内の成分にヘモグロビン(Hb)と呼ばれる成分がある。
ここでは、このヘモグロビンについて確認していこう。
体内に摂取された多くの鉄分は主に血液内に大半が滞留している。
※鉄は血中内に含まれている
一般的に血液は赤色をしている。
この赤い色素の元となっているのがヘモグロビンと呼ばれる成分だ。
もしヘモグロビンが青色だったなら血液は青色になるということ。
このヘモグロビンは幾つかの成分で構成されているがその主力となっている主力の成分が鉄分である。
※鉄分はヘモグロビンを構成する主力成分!
という事で鉄分はヘモグロビンの材料となり、血中内に存在するヘモグロビンの内部で元気に活躍していることになる。
◆鉄分を失うとヘモグロビン濃度が低下する
「鉄分を大量に失うとどうなるだろうか?」
答えは簡単。
ヘモグロビンを生成できなくなってくる。
現実的には貯蔵鉄と呼ばれるストックが存在するため、完全に鉄分が体内から消えてなくなることはないのだが、ヘモグロビンの材料である鉄分が不足するとヘモグロビンの生成能力が単純に低下するのである。
※原料の鉄分が減るとヘモグロビンが生成できない
◆スポーツジムではトレッドミルやエアロバイクといった有酸素運動マシンが人気が高い
「ヘモグロビンの最も大切な仕事はいったいなんだろうか?」
そう酸素の運搬である。
ヘモグロビンは酸素と結びついて血液中に溶け込み体の隅々にいたるまで酸素を供給している。
※ヘモグロビンは酸素を全身に運搬する
人間は酸素がなければ生きられない。(二酸化酸素も同様)
その為、酸素の運搬を行うヘモグロビン量の低下は人体に悪影響を及ぼし、貧血などの症状をもたらすのである。
◆有酸素運動マシンは持久力を高める
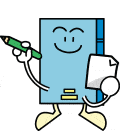
持久力を鍛えるトレーニングをしようと思えば、誰もが心肺機能を高めるトレーニングを優先して行うだろう。
スポーツジムではランニングを行うトレッドミルやダイエットの定番マシンであるエアロバイクといった有酸素運動マシンが人気が高い。
しかし、これらも心肺機能の向上をもたらすトレーニング種目である。
この心肺機能を高める有酸素運動トレーニングの根っこにある狙いは酸素摂取量の増加が目的。
効率よく酸素を摂取する能力を高めるためのトレーニング。
もう一歩踏み込んで言えば、効率よく体内の二酸化炭素濃度を排出する循環システムの構築を目的としたトレーニングを行っているとも言える。
当然トレーニングを行っている本人はこんな事は考えてもいない。
ダイエットが目的であったり、美容が目的であったりする。
◆酸素がポイント?
このようにスタミナをつける為に行われるトレーニングが着目している点に「酸素」という不可欠な成分がある。
酸素を多く取り込む能力が高まるほど、長時間の運動が可能となるからだ。
また二酸化酸素の排出が上手なアスリートの持久力が高いことも確認されている。
体内の酸素濃度は、持久系のスポーツや長時間のパフォーマンスに多大な影響を与えるのだ。
※体内の酸素濃度は競技に影響を与える
この重要不可欠な酸素を運搬する働きをもつのがヘモグロビン。
そしてこのヘモグロビンを生成する材料となっているのが鉄分。
鉄分と持久力の関連性が少しずつ見えてきたのではないだろうか?
◆汗と一緒に鉄分やナトリウムなどのミネラル成分も体外へ
運動を長時間継続して行うと人体には様々な変化が発生しはじめる。
まず最初に発生する変化は運動エネルギー源の燃焼。
運動エネルギーを得る為にブドウ糖を燃やし始め、その後脂肪やグリコーゲンの代謝に至る。
これらのエネルギー代謝が行われると、その代謝産物として幾つかの成分が筋肉や血中内に残留する。
また、体温の上昇を防止する為に、皮膚からは発汗が行われ気熱で皮膚温度の調整がなされる。
この際、汗と一緒に鉄分やナトリウムなどのミネラル成分も一緒に対外に放出される。
◆運動性貧血とは?
長時間有酸素運動が継続的に行われると、汗と共に大量の鉄分が流れ出て血中内のヘモグロビン濃度の低下現象が見られるようになる。
ヘモグロビン濃度の減少は酸素供給量の低下につながり、全身の細胞組織に十分な酸素を送り届けることができなくなり貧血症状を発症するようになる。
このように継続的な運動によって発生する貧血を運動性貧血と呼ぶ。
※運動によって鉄分が欠乏する貧血=運動性貧血
貧血に至るメカニズムは前項で解説した鉄欠乏性貧血と同様。
酸素の不足である。
◆酸素供給量が低下すると心肺機能・持久力・体力も低下を招く
ここまで鉄分と持久力、スタミナの関連性について解説してきた。
ひとつここで結論をまとめておこう。
※鉄分と持久力は直接関与はしない。
しかし、ヘモグロビンの主力となる材料である鉄分と持久力は切っても切れない関係にあると断定できる。
鉄の持久力に関する関連性の流れを順に追ってまとめると以下のようになる。
【鉄と持久力の関連性】
1.発汗による鉄分の流出
鉄が血液内から不足するとヘモグロビン濃度が低下する。
2.血中ヘモグロビン濃度の低下
ヘモグロビン濃度が低下すると酸素供給能力が低下する。
3.酸素供給能力の低下
酸素供給量が低下すると心肺機能が低下し持久力が低下する。
4.運動性貧血の発症
鉄が不足した状態で運動を継続すると場合によっては運動性貧血を発症しやすくなる。
以上が運動によって鉄が欠乏することにより発生する問題の流れである。
◆改めて鉄分と持久力の関連性を問う
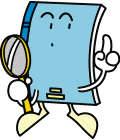
鉄分と持久力の関連性は直接ではないものの大きく影響を与えていることは事実。
スポーツアスリートは大会などの大舞台では最高のパフォーマンスを発揮したいもの。
しかし本番よりもむしろ、日々の練習の時こそタフなトレーニングを積んでおきたいと考える方も多いのではないだろうか?
最高の練習ができるように、最高のパフォーマンスが発揮できる状態を整えておく。
練習も真剣に取り組んだならば後半になれば誰もが苦しいはずだ。
この苦しい場面の練習こそが身となり骨となる。
周りのメンバーよりも一歩上のハードな練習を求めるならば鉄分の重要性をもう一度改めて考えてみよう。
◆鉄分摂取のポイント!ビタミンCを同時に摂取すると体内への吸収率が高まる
スポーツアスリートが長時間に渡って酸素の供給能力を確保できれば、それは大きなアドバンテージともなる。
運動中の水分やミネラルの補給は今では当たり前になっている。
今後、長時間に渡る運動を行う場合は「鉄分の補給」に関しても意識してみると良いだろう。
尚、鉄分の摂取に関しては食事からの摂取が基本である。
鉄分が豊富な食品でも触れたとおり、鉄分含有率が高い食品を積極的に摂取するとよいだろう。
特に海藻類は含有率のみならず、人体への吸収率も高いのでお勧めだ。
◆サプリメントから摂取するポイント
鉄分含有サプリメントはかなり多い。
昔は鉄分の影響食品としてミキプルーンが有名であったが、現在はペプチド状に加工された吸収率の高いサプリメントも製品化されている。
試合直前の補給や、試合のインターバル期間中に補給を行う際は、これらの消化吸収が早いサプリメントを摂取するとよいだろう。
サプリメントは海外製がかなり多いが、日本と海外では認められている成分が異なるので海外製のサプリメントを使用する場合は注意が必要だ。
単価が安いから・・・・と海外製を好む方も増えたが、安価であることよりも成分の充実度、安全性の方が重要であることは言うまでもない。
※価格よりも安全性・配合成分を重視
個人的には日本製がお勧め。可能であれば製造工場までも日本製の方が安心である。
尚、試合直後の場合は、消化吸収が良くビタミンも栄養素も豊富な「バナナ」の摂取も効果的だ。
◆鉄分の吸収を高めるビタミンC

余談だが、鉄分の体内への吸収を大きく助ける栄養成分がある。
その代表がビタミンC。
経口服用で鉄分を摂取する場合(点滴以外は大抵は経口のはず)はビタミンCを同時に摂取すると体内への吸収率が高まる。
サプリメントで摂取する場合は、マルチビタミン系サプリメントと鉄を同時に摂取するとよいだろう。

